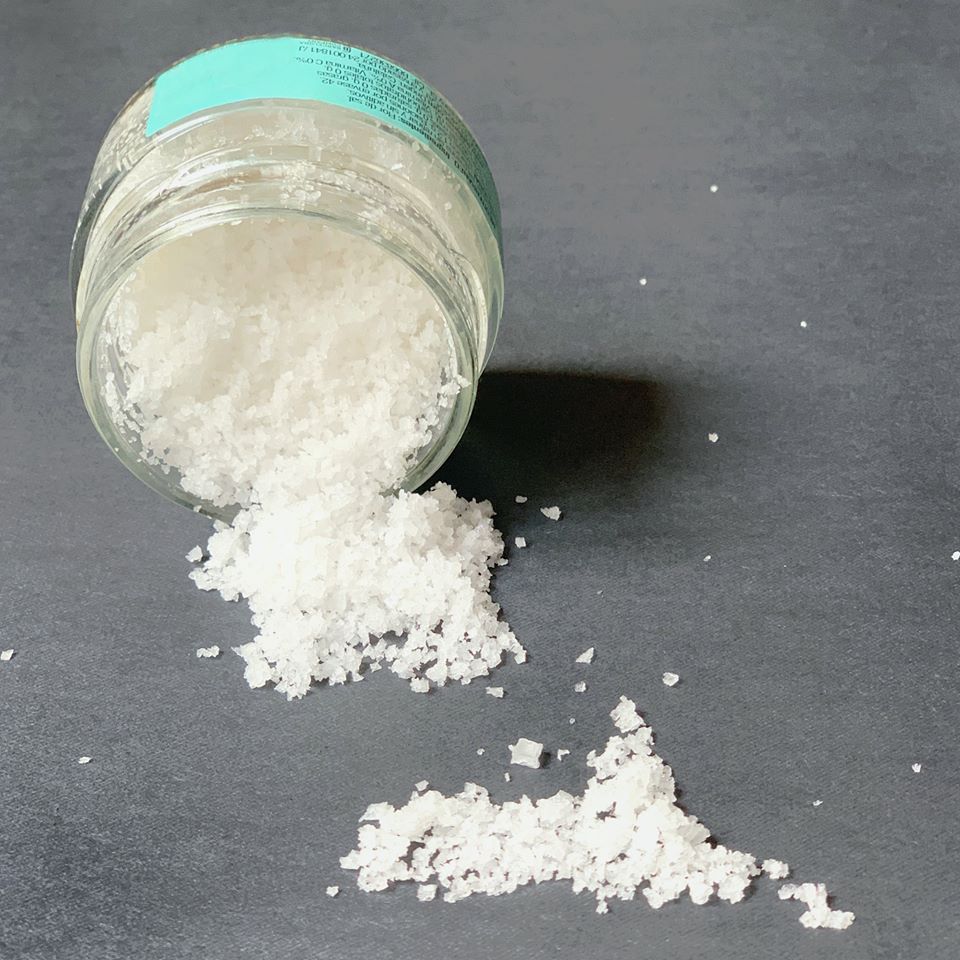【文】フアン・ムニョス 【構成・訳・写真】原田郁美
スペインの夏を象徴する冷製スープ、「ガスパチョ」。その爽やかな酸味と野菜の豊かな風味は、日本でも少しずつ親しまれるようになり、2013年には京都のスペイン料理界の有志グループ「D.O.KIOTO」によって、8月1日が「ガスパチョの日」として制定されました。それ以降、普及活動が続けられ、ガスパチョは日本でもより身近な存在になりつつあります。
きっと多くの方(スペイン人も含めて)が、ガスパチョと聞いて思い浮かべるのは、赤く輝くトマトの冷たいスープではないでしょうか。けれども実際には、ガスパチョには古くからの長い歴史があり、地域ごとに異なる味わいや調理法が存在します。それぞれのスタイルに、その土地ならではの物語や暮らしが息づいているのです。
今回の「Spanish Lifestyle」は、スペインワインとガストロノミー界の巨匠であり、世界に1万人以上のプロフェッショナルを送り出しているフアン・ムニョス先生が語る、ガスパチョの歴史をご紹介します。暑い夏に寄り添う、スペイン発祥のヘルシーな夏の冷静スープ、"ガスパチョ"のストーリーを、ぜひお楽しみください。

Juan Muñoz フアン・ムニョス
Master Sommelier
ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ(ASMSE)会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ(1987年)、スペイン最優秀ソムリエ(1993年)、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター(2007年、ロンドン)など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト(1992年)。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。
@juanmunozramos
ガスパチョの起源と歴史

ガスパチョについて語ると長く、そしてとても興味深い話になります。もともとはローマ時代に起源をもち、季節や地域、伝統的な野菜の栽培によってさまざまなバリエーションが存在します。
ガスパチョとは、オリーブオイル、酢、水、生の野菜(きゅうり、トマト、ピーマン、にんにくなど)を使って、サラダをすりつぶしたり叩いたりしたものです。私の生まれたグラナダ県カンポテハルでは、決してペースト状にはせず、生の野菜を大きめに切ってパンのかけらと一緒に食べていました。
面白いことに、ガスパチョについて話すとき、いつも「すりつぶすかどうか」という話になりますが、「ガスパチョ」という言葉自体はポルトガル語に由来し、「かけら」や「断片」を意味しています。また、「acho」や「cacho」という言葉は、モサラベ語の接尾語「acho」に由来し、パンのかけらを指しています。
他のガスパチョは、苦いオレンジのかけらやアーモンド、そら豆、小麦粉などを使って作られていました。これらが最も古いガスパチョであり、トマトが加わるのはアメリカ大陸発見以降のことです。
もともと夏の料理であり、熟したトマトに含まれる天然の色素「リコピン」が特徴的です。この料理は、スペイン南部のアンダルシア地方発祥とされており、暑い一日を乗り切るために、農夫たちは、ほとんどガスパチョで栄養をとっていたと言われています。
ガスパチョの変遷をたどる

パンのかけらを使ったガスパチョは、野菜を使う以前から存在しており、その起源はアル=アンダルス時代にさかのぼります。
最も原始的なガスパチョはもともと温かい料理であり、現在もラ・マンチャ地方やアリカンテ地方でその形態が残っています。その元の名前は「カッカバセウス(caccabaceus)」で、「鍋職人(カルデレロ)」を意味し、「カルデロ(鍋)」や「カルデレタ(小鍋)」の語源となっています。これはローマ時代のことで、パンを熱湯やその他の材料と共に鍋に入れて調理していました。
この調理法は中世まで続き、中世になると「ガスパチョ」という言葉が使われ始め、硬くなったパンのかけらを水、酢、オリーブオイル、塩に浸し、主にアーモンドやにんにくなどの材料を加えて作られていました。
この料理は「冷たいスープ(sopas frías)」と呼ばれ、その一種に、ユダヤ人街で典型的だった「メンジャール・ブラン(menjar blanc=白い食べ物)」というものがありました。
ガスパチョの種類と地域差

Spanish Lifestyleでもご紹介した、バルセロナ・ゴシック地区の
レストラン「El Cercle」のサルモレホ
ガスパチョとは、本来、パン、オリーブオイル、酢、塩、そして各家庭や季節ごとにある材料を使って作られる、あらゆる種類のスープやペースト(すり潰したもの)を指していました。これらは火にかけた大鍋で調理され、中世頃には冷製でも作られるようになったと考えられています。
現在のガスパチョの多様な種類は、主にスペイン南部とポルトガルに起源を持ちますが、「アンダルシア風ガスパチョ」と呼ばれる、パンと野菜を細かく砕いたり刻んだりしたタイプが特に有名です。
アホブランコ(Ajoblanco)
最も古いガスパチョとしては、「アホブランコ(Ajoblanco)」、「ポーラ・デ・アンテケラ(Porra de Antequera)」、「サルモレホ(Salmorejo)」が挙げられます。トマトを使った赤いバージョンは、19世紀半ばにトマトが食材として加えられてからの比較的新しいものです。
なかでも、アホブランコは最も古く、ニンニクをすり潰し、その時代の野菜、パン、酢、オリーブオイルなどと合わせたことに始まります。その後、アーモンドやナッツ類を加えるバリエーションも生まれました。
ドン・キホーテに登場する、温かいガスパチョ

また、温かいガスパチョの代表例には、「マンチェゴのガスパチョ(Galianos)」や、うずら、野うさぎ、ウサギなどの狩猟肉を使ったものがあり、そのベースには「トルタ・デ・パン・アシモ(Torta de Pan Ázimo)」というユダヤ人の無発酵パンが使われています。
これらはドン・キホーテがいつも語るガスパチョであり、大鍋で狩猟肉の切り身を見事なソースとともに煮込む料理です。これはアルバセテ県全域やラ・マンチャ地方の他の地域でも広く知られています。
特にウサギのガスパチョで最高と評されるのは、ムルシア州のラスポイ(Raspay/Raspai)村近郊、フミーリャとアリカンテの国境にあるピノソ(Pinoso)周辺で作られるもので、まさに芸術品と言える一品です。
また、漁師のガスパチョとして知られるものは、カンペリョ(Campello)という町で作られ、魚の切り身をサフランとともにじっくりと煮込んだ料理です。
地中海ダイエットを代表する
「アンダルシア風ガスパチョ」

夏には、アンダルシアのガスパチョに勝るものはありません。材料は地域によって多少異なりますが、文明の利器であるミキサーの登場によって、ガスパチョはより手軽に作れるようになり、今では夏の食卓に欠かせない一品となりました。素材そのものの栄養を活かした、自然でヘルシーな冷製スープは、忙しい日々の中でも無理なく身体を整えてくれる存在です。
基本の材料は、トマト、ピーマン、にんにく、パン、キュウリ、時には玉ねぎ、そしてオリーブオイル、酢、塩、水です。場合によっては、にんにく、オイル、酢、時にクミンなどのスパイスを、歴史ある「アルミレス(乳鉢と乳棒:almirez)」でつぶし、そのペーストを水とともに加えていきます。
まずは、にんにくと塩を「ドルニジェロ(dornillero)」と呼ばれる木製のすりこぎでつぶし、クリーミーなペーストを作ります。そこに刻んだトマトを加え、続いてオイル、酢、水を好みで加えます。最後に玉ねぎ、キュウリ、ピーマン(場合によっては)を細かく刻んで入れます。
ご覧の通り、最初はにんにく、オイル、酢、塩と浸したパンの話から始まり、白いアーモンドなどのナッツ類が加わり、アメリカ大陸発見後にトマトやピーマンが取り入れられ、今日に至ります。
ガスパチョは今や国際的な料理となり、多くの人に合う健康的な食事法として知られています。まさに地中海式ダイエットの代表格であり、医者にかかるようなもの—これ以上自然な食べ物はありません。
私は、最近流行りのスムージーよりもガスパチョの方が好きです。
最高のガスパチョとは?
お話してきたように、スペインには冷製・温製を問わずさまざまな種類のガスパチョがあり、地域ごとに少しずつ異なるのが魅力です。でも、それこそがガスパチョの面白さ。ことわざにもあるように、「最高のガスパチョは母の味」。それに勝るものはありません。
また、サラダと同様に、ガスパチョを作るには3〜4人のキャラクターが必要です。
塩には「ケチな人」、酢には「冷静な人」、オリーブオイルには「寛大な人」、
そして時にはよくつぶすための「狂った人」が。
SALUD Y AMOR…..MUCHO AMOR
フアン・ムニョス – あなたのソムリエ
最後に
フアン先生のガスパチョのお話、いかがでしたか?
筆者自身も初めて知ることが多く、一杯のガスパチョには、スペインの風土や人々の暮らしが豊かに映し出されているのだと、あらためて実感しました。
特に、「アンダルシア風ガスパチョ」は、暑さで食欲が落ちやすい夏の栄養補給にもぴったりですね。ぜひお近くのスペインレストランやご家庭で、本場の味わいを楽しんでみられてはいかがでしょう。爽やかな酸味と野菜の豊かな風味、ビタミンたっぷりの夏の冷製スープが、暑い日々をヘルシーでさわやかに彩ってくれることでしょう。

Ikumi Harada 原田郁美
Journalist & Creative Director
スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会(AGE)」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist(ICEX認定)。山口県出身。
@ikumiharada