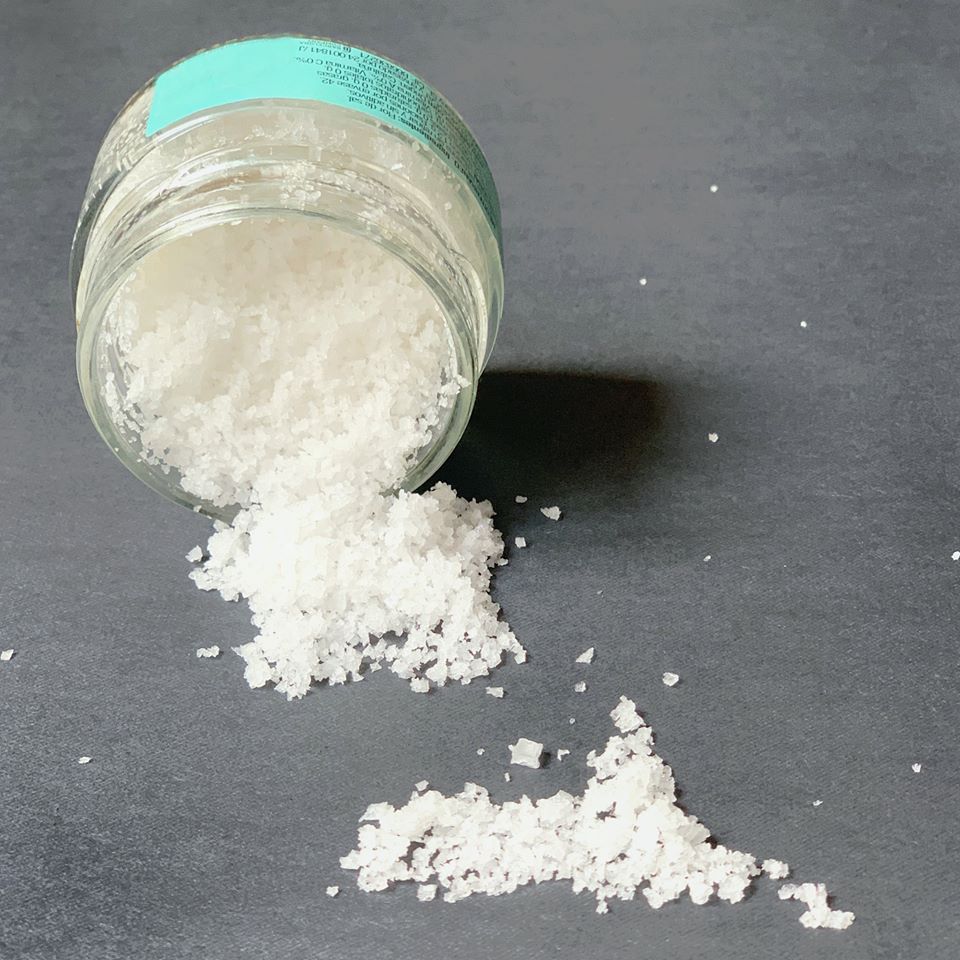世界中のワイン専門家や愛好家から注目され、日本でも人気が高まっている「カナリア諸島のワイン(Canary Wine)」。カナリア諸島は、スペイン領の群島で、大西洋上、アフリカ大陸の北西沿岸に近い位置にあります。火山活動によって生まれた島々で、グラン・カナリア島、テネリフェ島、フエルテベントゥーラ島、ランサローテ島、ラ・パルマ島、ラ・ゴメラ島、エル・イエロ島から成り立っています。
テネリフェ島にある、スペイン領内最高峰のテイデ火山
標高3718m。海底からの高さはおよそ7500m
カナリア諸島のブドウ栽培は、15世紀にヨーロッパの植民者たちによってもたらされました。しかし、この地のブドウは火山性の環境に適応し、500年以上にわたり人々が最適な品種を選びながら自然と共に進化してきました。世界的なフィロキセラ禍を免れたブドウたちは、唯一無二の進化の過程を示す標本として、長い間、世界の研究者たちの注目を集めてきました。
そんな中、8月上旬、収穫が始まった直後に届いたのが、これまで被害のなかったテネリフェ島で初めてフィロキセラが確認されたというニュースでした。そこで、テネリフェ島を代表するワイナリーのひとつViñátigo(ビニャティゴ)で醸造を担い、ブドウ栽培にも精通するホルヘ・メンデス氏に話を聞きました。
ホルヘ氏はラ・ラグーナ大学で農業・農村環境工学を学び、マドリード工科大学でブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。世界各地の銘醸地で経験を積んだのち、父フアン・ヘスス氏のワイナリーをいずれ継ぐ2代目として、またメンデス家5代目としてワイナリーを担っています。国際的なワインカンファレンスでも登壇し、ブドウ栽培家としても国内外から注目を集める存在です。
「フィロキセラの問題は複雑ですが、現時点ではコントロールされています」
とのこと。発生は島の北東部、バジェ・デ・ゲラ、テヒナ、タコロンテの町々に限られており、放棄された畑や稼働中の畑の両方で検査が行われています。他の地域では新たな発生は確認されていません。

カナリア諸島には83品種の土着品種が存在し、そのうち40〜50%は固有品種です。100年以上の自根のブドウ畑も多く残っており、500年にわたる伝統を守る貴重な遺産となっています。
8月22日『カナリア諸島官報(BOC)』では、テネリフェ島で局所的に発生が確認されたフィロキセラ(学名:Daktulosphaira vitifoliae Fitch)の存在が正式に宣言され、拡散を防ぐための緊急防除・管理措置が定められました。

Juan Muñoz フアン・ムニョス
Master Sommelier
ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ(ASMSE)会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ(1987年)、スペイン最優秀ソムリエ(1993年)、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター(2007年、ロンドン)など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト(1992年)。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。
@juanmunozramos
フアン先生のフィロキセラについてのレクチャーと見解
フィロキセラは1800年代末に世界中で被害をもたらし、多くのブドウが接ぎ木に切り替わる原因となったブドウネアブラムシです。しかし、チリやカナリア諸島、一部の砂地の畑ではこの害虫は生きられませんでした。数年前にカリフォルニアで突然変異が発生し、現在ではカナリア諸島でも同様の事例が報告されているとのことです。火山性の土壌では害虫に影響されませんが、砂の割合が少なく他の土壌と混ざった畑では発生する可能性があります。これはあくまで事例として限定的であり、広範囲に拡大しているわけではありません。(8月29日現在)
世界でも類を見ない三つ編み仕立て
コルドントレンサード
カナリア諸島の原風景を守るために

コルドントレンザード(三つ編み仕立て)
テネリフェ島のラ・オロタバでは、枝を編み込んで水平に伸ばす「コルドントレンザード(三つ編み仕立て)」という、世界でも稀有な栽培方法が受け継がれてきました。本来はマルヴァジア栽培のために生み出されたものです。50〜60年前までは、島の人々が生活の糧を得るため、ブドウの下で穀物やジャガイモを育てる二毛作も行われていました。
■詳細はこちらから↓
<ビニャティゴ>特別講義:テネリフェ島でコルドントレンサードが生まれた理由 Vol.2-第12回スペインワインと食大学
テネリフェ島、そしてカナリア諸島の土着品種やワイン文化遺産、この地ならではの原風景を守るために、いま島の造り手たちは力を結集しています。その歩みに寄り添い、少しでも力になれるよう、心からの敬意とエールを送りたいと思います。筆者自身もまもなく現地を訪れ、この大切な時期を共に感じながら、造り手たちの声を皆さまへお伝えしていくつもりです。
【関連記事】
ビニャティゴ~カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー
【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」
火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム

Ikumi Harada 原田郁美
Journalist & Creative Director
スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会(AGE)」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist(ICEX認定)。山口県出身。
@ikumiharada