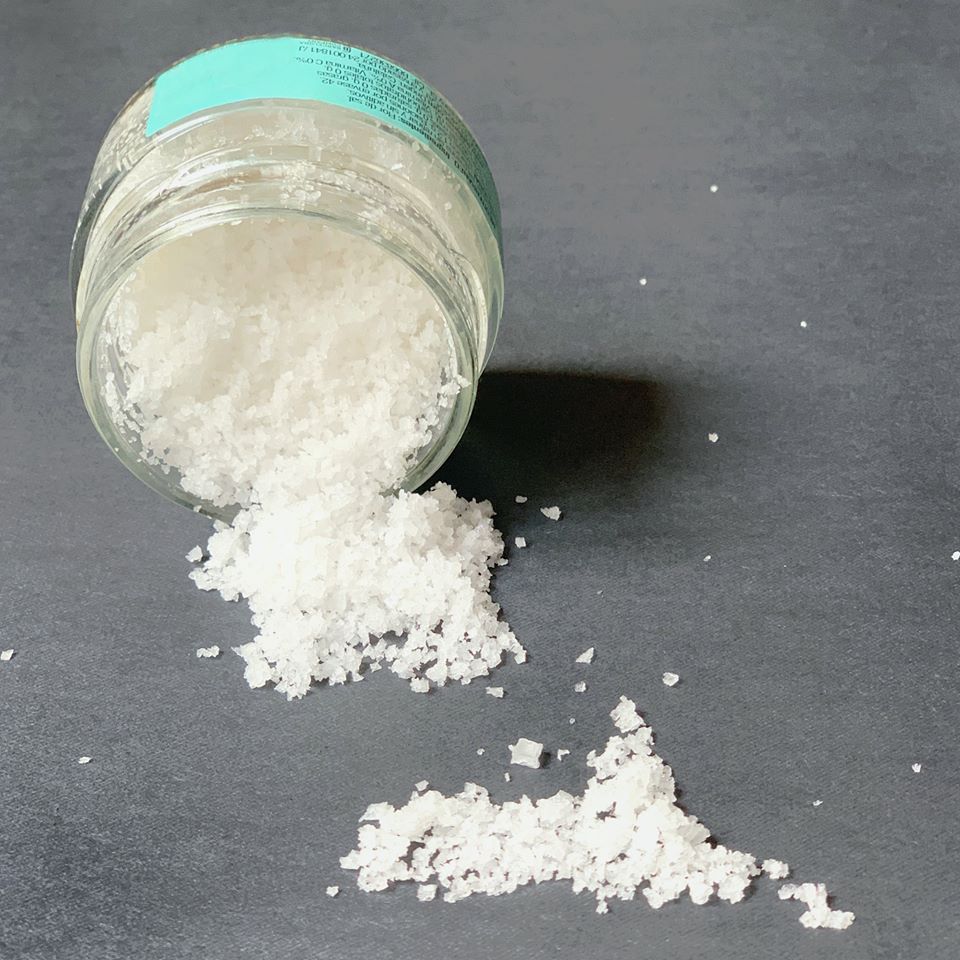ボデガ・チャコリ・レサバルのオーナーご夫妻とチャコリで乾杯。
【文】フアン・ムニョス【訳・写真】原田郁美
今回のSpanish Lifestyleでは、これからの季節にぴったりな爽やかなワイン「チャコリ」にフォーカス。バスク地方のビルバオとサン・セバスティアンを訪れるにあたり、スペインのマスターソムリエ、フアン先生がチャコリの魅力と進化について特別レクチャーをしてくださいました。

Juan Muñoz フアン・ムニョス
Master Sommelier
ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ(ASMSE)会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与。カタルーニャ最優秀ソムリエ(1987年)、スペイン最優秀ソムリエ(1993年)、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター(2007年、ロンドン)など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト(1992年)。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。@juanmunozramos
バスク地方(エウスカディ)を訪れるのはいつでも喜びに満ちた体験ですが、そこに“ワイン”という目的が加われば、その喜びは何倍にも膨らみます。
ぶどう畑と森、古い石造りの農家(カセリオ)が点在する丘陵地帯が、青く荒々しい海に向かって傾斜しながら続いている—そんな風景に出会った瞬間、自分が絵葉書の中に入り込んでしまったかのような感覚に陥ります。そして、グラスを手にワインを味わうとき、もしも固定観念を捨てて心を開いて向き合えば、そこにはガス入りの軽い白ワインというイメージを超えた、偉大な白ワインの世界が広がっているのです。チャコリは、かつてバルでヒルダやピンチョスに合わせてグラスの中で弾けるように飲まれていた“酸っぱいフレッシュなワイン”から、個性・風土・品質を兼ね備えた、真に優れた白ワインとして高く評価されるようになってきました。熟成によって超熟タイプも増え、ワイン愛好家たちの注目を集めています。

特別な注ぎ方「エスカンシア」ワインを高いところからグラスに注ぐことで、
高い酸をまろやかにする。
もちろん、若々しく軽快なスタイルのチャコリも大切な存在です。アペリティフとして親しまれるバルのチャコリに反対しているわけではありません。むしろ、多様なスタイルが共存しながら、チャコリ全体の世界が豊かになっているのです。シュール・リー熟成、長期瓶内熟成、樽醗酵・樽熟成、遅摘みぶどう(VT – ベンディミア・タルディア )による甘美な酸味のあるタイプ、さらにはスパークリングまで、今やチャコリの進化はとどまるところを知りません。
「気候・ぶどう・土壌・人」—この四位一体の要素が見事に調和した結果、チャコリは国内外で高く評価される白ワインとなったのです。
チャコリの産地とぶどう畑

カンタブリア海を見下ろす、ボデガ・チャコリ・レサバルのブドウ畑。
バスク地方のワインの独自性は、その自然環境に深く根ざしています。海に近い丘陵地で、ぶどうの栽培には千年以上の歴史があります。土壌は水はけの良いシリカ質(ケイ酸質)、粘板岩質、ゆるい砂質で、500メートル以上の高地に80年を超える古木が残る区画もあり、斜面の傾斜が30%を超える場所での栽培も珍しくありません。テラス状に広がる畑や点在する小さな区画は、この地の地形の複雑さを物語っています。
チャコリの語源のひとつは「Etxeko egin(家で造った)」——つまり「自家消費のために造るワイン」。
1975年に出版された『スペインのぶどう畑』という書物でも「売るためではなく、自分たちの喜びのために造られるワイン」として記されています。
チャコリの歴史
美食の街サンセバスティアンから西へ20kmに位置する漁村ゲタリアのワイナリー チョミンエチャニス。
バスク大学のウベルト・アスティビア教授によれば、“チャコリ(Chacolí(スペイン語)/Txakoli(バスク語))”とはバスクのみならず、フランスのイルレギ(Irouléguy)やカンタブリア東部(現在のIGPコスタ・デ・カンタブリア)などにもかつて広く使われていた名称で、気候的にもワインスタイル的にも連続性があります。
ナバーラ州のパンプローナ盆地には「チャコリンゴリ(Txacolingorri)」という呼び名があり、さらにミランダ・デ・エブロやブルゴス県のメナ渓谷(チャコリ・デル・バジェ・デ・メナ)まで広がっていました。これら後者の地域はより地中海気候に属するため、よりカスティーリャ的な気候に適したガルナッチャやテンプラニーリョといったブドウ品種が用いられていました。こうして、川や盆地に沿って大西洋気候が内陸へと入り込んでいたのです。
これは誰かを否定する意図ではまったくなく、むしろ「チャコリ」は、大西洋に面したブドウ畑や川がカンタブリア海〜大西洋へと注ぐような地域で、「大西洋的なワイン」として理解されやすい、ということを示しているのです。もちろん、それぞれの土地の土壌・気候・品種・人の手が異なるため、スタイルも実に多様です。
1877年の『マドリード・ワイン博覧会記録』には、ビスカヤにおいてフランス系の白ぶどうが主要品種であり、新しい植栽のほとんどを占めていたことが記されています。
赤ワイン用品種としては、バルトルメサ、グラシアナ、プリエタ、セーニャ、ベルデハなどが挙げられ、アルビージャス(Albillas)は主に食用とされていました。同書によれば、当時のギプスコアではぶどう栽培の規模が非常に小さく、ほとんど熟さない質の低いぶどうしかなかったとも記されています。
チャコリの伝統と現代

チョミンエチャニス。フレンチオークで14ヶ月ほど樽熟成したチャコリ。
昔のチャコリは、10月中旬(ピラール祭の頃)に収穫され、古い木樽(クペラやボコイ)で発酵されました。沈殿した澱が自然に落ち着き、ワインが澄んできたところで濾過せず瓶詰めされ、瓶内でマロラクティック発酵や二次発酵を起こすこともあり、自然な微発泡をともなっていました。これがチャコリの“ガス感”の起源であり、酪農とともにあったこの地の生活文化を反映しています。
現代のチャコリは、大西洋の冷涼な風土と鮮烈な酸を活かしたスタイルで、日々進化を遂げています。収量を厳しく制限し、区画ごとのブドウを選別、シュール・リーや樽熟成、フードルやアンフォラ、セメントタンク、さらにはフロール(産膜酵母)下での熟成など、多彩な醸造法が取り入れられています。スパークリングや甘口などのスタイルも登場し、まさに品質と多様性を兼ね備えたワインへと進化を遂げています。また、チャコリは海を越え、バスク系移民によってチリでも歴史的に造られており、近年再評価が進んでいます。
3つのDOと多様性

D.O. Getariako Txakolina(D.O.チャコリ・デ・ゲタリア)
D.O. Bizkaiko Txakolina(D.O.チャコリ・デ・ビスカヤ)
D.O. Arabako Txakolina(D.O.チャコリ・デ・アラバ)
3つある原産地呼称(DO)の中でも、ゲタリアのチャコリは“最も純粋なチャコリ”として知られています。一方で、ビスカヤやアラバのDOは、それぞれに新しい個性を打ち出し、スタイルの幅を広げています。内陸部にあるオラベリア村のベンゴエチェなどは、降水量が少なく、ナバーラからの冷たい夜風が入りやすいなど、ユニークな気候条件を持っています。
ビスカヤの代表的な産地は、海沿いのバキオや内陸のバルマセダ。イチャスメンディなどの造り手は、レイオアやエランディオといった沿岸地域から、モルガやドゥランゴの高地にかけて、約1ヶ月も収穫時期に差が出るという繊細なマイクロクライメイトを丁寧に活かしています。
ギプスコアでは、伝統的にシドラ(りんご酒)とチャコリが共存し、地元の風土や文化を象徴してきました。
バスクではシドラ(シードル)とワインが共存し、いずれも民俗文化の一部として発展してきました。低アルコール(9.5~10度)のブドウを10月に収穫し、古樽で発酵。ワインが自然に澄んでから瓶詰めされるため、瓶内には澱が残ることもありました。このような素朴で自然な造りが、バスクの風土とともに今も大切にされています。
かつてのチャコリは、発酵を終えたばかり、あるいは瓶内でマロラクティック発酵を行っており、特有の発泡感(炭酸ガス)を伴っていました。そしてこの発泡が強ければ強いほど人気があり、高値で取引されていたのです。つまり、伝統的なチャコリは、炭酸を持ち、できるだけ早く(その年内に)飲まれるワインだったのです。。しかし現在、その状況は大きく変わりました。チャコリは高品質な白ワインの選択肢としての地位を確立し、多彩なスタイルが生まれています。
中でも注目すべきはチャコリのスパークリングワインです。その代表が《イサル・レク(Izar-Leku)》。この地域において、低アルコールで高い酸を備える土地の特性が、スパークリングワインに理想的な条件となっています。
また、樽を使用したチャコリも見逃せません。発酵や熟成に大樽を用いた伝統的なスタイルは、クリーミーな質感と生き生きとした酸、そして際立つバランスによって、熟成によるポテンシャルを感じさせてくれます。特に小樽よりも大樽で仕上げたものは、木樽の主張が控えめで、ワインの本質がより豊かに表現されます。
甘口チャコリ(遅摘み)もまた魅力的な存在です。糖と酸のバランスは、若いうちも熟成後も人を惹きつける魅力を持ち、デザートやブルーチーズとの相性も抜群です。
さらに、驚くべきは赤のチャコリ。特に伝統品種《オンダリビ・ベルツァ(Hondarribi Beltza)》を用いたものは、初めはやや酸やタンニンが際立つものの、それこそがこのワインの個性であり、青魚との相性は格別です。近年では《ロサード(オホ・デ・ペルディス)》タイプも登場し、タパスやピンチョスに最適、あるいは夕陽を眺めながらゆっくりと一杯楽しむのにもぴったりなスタイルとして人気を集めています。
チャコリのブドウ品種
◯白ブドウ【オンダリビ・スリ(Reira – Hondarribi Zuri / Corbu Blanc)】
アラバ地方では紀元760年には既にブドウ栽培の記録があり、ビスカヤでは8世紀から、13〜15世紀には広く植えられるようになりました。1877年には3つの大きな病害(フィロキセラなど)により危機を迎えますが、1989年に再植プログラムが始まり、1994年にD.O.チャコリが正式に認定されました。カンタブリア地方では19世紀まで広く栽培され、ブルゴスでも17世紀にはその存在が記録されています。この品種の特徴は、中くらいの房、小粒で丸く黄金色を帯びた果粒、搾汁率の低さです。
●黒ブドウ【オンダリビ・ベルツァ(Hondarribi Beltza)】

スク地方原産の黒ブドウ品種で、フランスとの国境をまたぐように分布しており、ナバーラ、カンタブリア、カスティーリャ・イ・レオンといった周辺地域でも栽培されています。この品種は、単一品種ワインとしても、他品種とのブレンドワインとしても利用されており、その存在感を高めています。
シノニムには、オンダラビ・ベルツァ、オンダルビヤ・ベルツァ、ベルデ・サリエ、ホンダラビ・ゴリ、オンダルビヤ・ネグラなど、地域による呼び名の違いが見られます。発芽は早く、熟成には時間を要する晩熟タイプで、短剪定による垣根仕立てや棚仕立てで栽培されますが、うどんこ病にはやや敏感とされています。
醸造面では、ポリフェノール含有量が高く、豊かな色合いとフルーティーな香りを持つことが特徴です。ワインとしては、色が濃く力強いスタイルでありながら、澄んだ味わいと高いアイデンティティを備えています。酸と果実味のバランスが良く、アルコール度数は最大で13%程度と、全体として調和の取れた仕上がりになります。
最後に
フアン先生によるチャコリ講義、いかがでしたか?ブドウの特性や地域の背景を知ることで、、次に味わう一杯がぐっと印象深くなるのが、ワインの魅力です。学びの後はいよいよ実践編—海と山に抱かれたチャコリの地を訪ね、その土地ならではの風土と造り手の想いに触れます。この続きは、Spanish Lifestyleのワイナリーレポートで。チャコリの真髄に出会う旅の記録を、どうぞお楽しみに。

Ikumi Harada 原田郁美
Journalist & Creative Director
スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会(AGE)」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist(ICEX認定)。山口県出身。
@ikumiharada